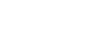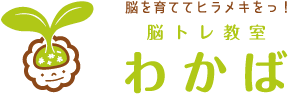川と包丁とスイカと学びがあふれる山の学校の夏2025
「子どもが自分から関わり合い、自然に笑いあう――そんな場所があるなんて思いませんでした」
はじめて参加された保護者の方から、そんな感想をいただきました。
山の学校の一日は、まさに“生きる学び”の連続です。
この日は、朝からみんなでカレー作り。
年齢も性格もばらばらの子どもたちが、野菜を洗い、皮をむき、包丁を握って真剣なまなざしで切っていきます。
「手を切らないように」「ここはこうやるといいよ」
自然と声をかけ合い、年上の子が年下の子を見守る姿も印象的でした。
午後は、お楽しみの川遊びとスイカ割り!
冷たい水の感触に歓声が上がり、夢中で遊ぶ中でも、年齢の違う子同士が自然と協力しあう様子が見られました。
目隠しをしてスイカを割るときも、「右だよ!もう少し前!」と声を合わせる姿に、仲間意識の芽生えを感じます。
昼食には、子どもたちの手でつくられたカレーライス。
「これ、ぼくが切ったにんじん!」「わたしが皮むいた!」と嬉しそうに話しながら、どの子もぺろりと完食。
自分で作ったごはんは、なによりのごちそうです。
山の学校が大切にしていること
山の学校では、“学び”は教科書の中だけではなく、「暮らし」や「遊び」の中にあると考えています。
年齢や立場に関係なく、子どもたちが自然の中で関わり合い、自分の力でできた達成感を味わう。
そんな経験が、彼らの心の根っこを育ててくれるのです。
この日、ある子がポツリとつぶやきました。
「また来たい。今度はもっと野菜切る!」
この一言に、すべてが詰まっている気がします。