7月19日 金曜日
大島の山の学校が始まりました。
今日のお昼ご飯は、ハッシュドビーフです。
お腹を空かせて帰ってくる子どもたちの為にご飯を7合炊きました。
多かったかなあ…と思っていたのですがお腹ペコペコで帰ってきた子供たち 食べる食べる。
あっと言う間に炊飯器のごはんが・・・空っぽ
お腹いっぱいになった子供たちとお昼からは、シーグラスとサンゴを拾いにいきました。
元気に子どもたちと夏を乗り切りたいと思います。
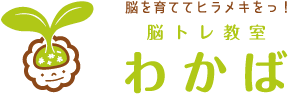
長崎市住吉町にある脳トレ教室

大島の山の学校が始まりました。
今日のお昼ご飯は、ハッシュドビーフです。
お腹を空かせて帰ってくる子どもたちの為にご飯を7合炊きました。
多かったかなあ…と思っていたのですがお腹ペコペコで帰ってきた子供たち 食べる食べる。
あっと言う間に炊飯器のごはんが・・・空っぽ
お腹いっぱいになった子供たちとお昼からは、シーグラスとサンゴを拾いにいきました。
元気に子どもたちと夏を乗り切りたいと思います。
わかばで一番小さいお友だちのゆうちゃん
4月から幼稚園に行きだしてたくさんの刺激を受けていて、脳もかなり活発に情報を送りあっているのが遊びを見ていると分かります。
今日は、積木を積みながら「イチ・ニ・サン」と数を数える姿が見られました。
一生懸命かぞえるんですよね。 もう、こちらの顔がほわーっと緩みっぱなしです。
丁度数に興味が出てくる月齢になってきているのでいい感じで脳が発達ているのがうかがえますね。楽しみ楽しみ。
今日の大島は霧の中にすっぽりかくれんぼです。
大島大橋の向こうは真っ白 まるで別世界へ飛び込んでいく感じがします。
なんと!! 神秘的な風景 長浦岳も濃い霧で車のすぐ先も見えないくらいで突然対向車が飛び出してきます。
異次元な空間の体験ができます。
さて、今日は月曜日 運動会疲れのお子さま方になんとか集中して考える時間を提供する為に今日は折り紙を使うことにしました。
脳を鍛えるというのは、「いかに考えさせるか」問題点を理解し問題の結論に(正しい答えとは限りません)到達するまでの脳の動き(信号の伝え方や繫ぐ回路を伸ばす)を良くするもので、生活の中のどんなことでも気づいたらそれが脳を鍛えることに繋がるのです。
指先を細かく使えることはとても大切です。
指を動かすことで脳に刺激を送ることが出来るからです。
はて! 折り紙をしながらお子さま方は何を感じ、何に気づいてくださるのでしょうね。楽しみ楽しみ。
今年もゴールデンウィークも終わりですね。
楽しい時間を過ごせたでしょうか。
授業は明日までお休みをいただきますが、お子さま方が楽しかった時間のご報告をしてくださるのが楽しみです。
先週の木曜日から角度の問題や面積の問題をアップしました。
流石に6年生は直ぐに答えを送ってくれました。
私、とても嬉しかったんです。さすがに6年生だなぁと思いました。
3年生や4年生くらいまでは、問題を見て面倒臭いと思うとなかなか考えようとしないお子さまもたくさんいらっしゃいます。
でも、そこをお父さんやお母さんの一押しで「やってみようかなぁ」ってお子さまは思うのです。
今回は、小学生の問題だと思われてスルーされたご父兄の方もいらっしゃったと思いますが、お子さまが小さくても、「わかばの宿題が解けたから先生に持って行って。」とお子さまに渡して頂けたらお子さまは何か感じることがあったと思います。
お子さまは、生活の中で体験したことを通していろんなことを学びます。
難しい問題をお父さんが解いて見せて「お父さんってやっぱり凄いなぁ」と感じたり、問題が分り易くなるように一緒に工夫してくれるお母さんの姿を見て「お母さんありがとう」って思ったり、今回、いろんなことを気づいたお母さんから感想をいただいたのでご紹介します。
Aさんからのメール
家族で面積の問題に挑戦しました。
答えは、10です。
ひらめきが足りず、子どもも自力では解けず、お父さんに教えてもらってました。
ほんの少しの時間ですが、とても良い時間を過ごすことができました。
ありがとうございました。
私の返信
今は家族で同じ家の中にいても個々で過ごす事が多くなってるとおもうのですが、こういう時間を過ごしながら大人って凄いなあ~と気づかせることが大切ですね。
お母さんからの返信
そうだと思います。
子育ても、私が子どもだった頃と変わってるところがあり、それは共働きの家庭が増えたり、近所付き合いも少なくなったりなど、色んな大人と接する機会が減った環境や、子どもの考えや意見を尊重してという子育ての考え方が、甘やかしに繋がってたりなどして、子どもが大人と同じなんだと思い違いをしてる時があるなと思います。
お父さんは凄いんだよと話しを聞くよりも、一緒の時間を過ごす中で子供自身が実感することが大事なんだなと思いました。
Bさんの感想
先生からの問題は、子どもがひとりで考えるにはなかなか難しいけれど、一緒に考え、わかったときの「あ~!」は誇らしげです。難しい問題に挑戦して、
「わかった!」
と目を輝かせている姿はわかばの醍醐味だと実感しています。
これからもよろしくお願いいたします。
今回は、小学生の問題だと思われてスルーしたご父兄もいらっしゃったと思いますが、小さなお子さまでも「わかばの宿題解いてみたから先生に渡してね。」とお子さまに託ていただけたらお子さまも何か誇らしく感じることが出来たのではないでしょうか。
ご家庭の中で、何かお子さまと共通の話題でお話をすることで大人ってすごいなあと思う機会はたくさんあると思います。
先ずは、生活の中で今お子さまが体験していることを話題にして簡単な質問をしてみるとか・・・
例えば、今日の夕食にはどんな材料が入っているでしょうか?とか、どんな順番で作ったでしょう。とか・・・
食事をしながら楽しい会話をすることでお子さまの脳は刺激され活発に情報を送りあい活性化します。
ちょっとした質問で大丈夫なのでぜひ1日のどこかで質問やお話をしてあげてみてください。
毎日毎日、お子さま方といろんなことをしながらお子さまが今どんなことを感じたのか。頭に入ってきた情報をどんなふうに分析しているのか? お子さまの行動や言葉を観察しながら分析します。
私が、この時期の遊びが以後の知能の発達にとても影響を与えると気づいたのは、私の息子を息子が3歳の頃から就学までに遊びながら脳を刺激してくれた母の遊びにありました。
息子は、母と遊びを始めてから半年ほど(3歳半頃)で言葉が爆発的に出るようになりました。そして、会社のロゴを見るとどこの会社かすべて答えられたり、当時はやりだった、東京から大阪までの新幹線の駅名をすらすらと言ったり・・・
これは、覚えさせた訳ではなくいつの間にか覚えていたもので覚えていることが分かった時には、驚きました。
そのうち、父が教えた野草の名前や効能などにも興味を持ち、お散歩での山に行くとヨモギや土筆を取ってきては、ヨモギ団子を作ったり、土筆のおひたしを作って食べました。
母の遊びは、その延長線上の最後にいつもたのしいことや美味しいことが待っているんです。
そんな遊びだと楽しくて楽しくて脳もたくさん刺激されますよね。
子どもの脳を刺激する遊びを教室ではたくさん紹介しています。そして、その刺激を受けて育った方たちが社会人になって自分の好きことを仕事にして活躍しています。
遊びが大好きでたくさんたくさん遊んでいるだけで賢く育つって素敵じゃないですか?
先週の金曜日は、満月でした。
みなさん!! 知っていますか?
いま、月には、日本の月面探査機が着陸しているんですよ。
裸眼で見ると黄色く輝く月しか見えませんが、携帯カメラZOOMしてみると「ここにいるんじゃないかな・・・」なんて雰囲気が見られます。
先週の金曜日を境に少しずつ小さくなっていく月ですが、お子さま方と宇宙の話してみませんか。
今年度最終授業の日でした。
2024年、最終授業を40回繰り返してきたことになります。
40年です。 長いようであっと言う間
最初は、知能教室が全国にもほとんどない時代 福岡の実業者が資源のない国日本は、子どもたちの知能を育てて「知恵」を資源として生きにいていく力にする。という目的で久留米に最初の教室が開設され、その後、福岡、長崎と続いて開設されました。
時代が変わればその時々の流れで子育ての方法も随分変わってきましたが…
人間としての育て方は変えてはいけません。
自分で考え、行動する。自分の人生を豊かに送るための脳の本質 それは、0歳から12歳頃まで
たった12年くらいの間に刻み込まれて完成するのです。
特に6歳の頃は、小学校へ入ってからの学習をいかに自分のものにしていけるか、その力をつけられる人とつけられなかった人の人生が大きく違ってくる年齢です。
6歳という大切の時を受験という目先の目的だけにとらわれ、知識を詰め込むだけの教育をしてしまうことは、その後のお子様の心に大きな重荷を残してしまうこともあります。
小学校へ入学することが大事なことではなく、小学校でいかに興味を持って学習に取り組み(話を聞く力・聞いた話を理解する力・考えたことを相手に伝える力・指示されたことに従える力を蓄える)、お友達と接しながら心も成長させられるか(コミュニケ―ション力・理解力。忍耐力・折り合い力の養成)、そのための準備期間と捉えて6歳の1年間はいろんなことを経験させてあげたいと思います。
なので、脳トレ教室わかばの年長クラスはいろんなカリキュラムを用意しています。
只今、6歳児クラスの新規募集を行っています。
お友達、お知り合いの今年年長さんになられるお子さまがいらっしゃいましたら、ぜひ、ぜひ、ご紹介をよろしくお願いいたします。
今週は、前半お休みしていたのでもう金曜日というのが・・・火曜日みたいな感覚です。
今日は、1歳半のゆうちゃんが来ます。
ゆうちゃんは、今わかばの教室生さんで一番若いお子さまです。
これからいろんな遊びを通していろんなことを覚えていくので、丁寧に話を聞かせたり、小さいながらも考えるきっかけを与えたり…
皆さんのお子様は1歳半くらいの頃はどんなことをして遊んでいましたか?
まだ、自分で何かをして遊ぶというより、周りを見ながら少しずつそれに興味を持って手を出して触って確かめてという時期だと思います。
今日は、ペットボトルのキャップに磁石を入れてゆうちゃんをそれを見てどんな反応を見せてくれるのか、観察しながらいろんな声かけや遊びを一緒にしてみたいと思います。
土曜日は、大島教室の日です。
朝から今日は、クリアーゲーム(おはじき飛び越しゲーム)で盛り上がりました。
今日は、小1くらいより通っていただいている現在6年生のお子さまのママがその様子を見学されていました。
大島教室の子どもたちは、大体3歳くらいから入室されるのですが、妹さんが入室された後にお兄ちゃんが入室されました。
いつもは、みんな同じくらいのペースで取り組まれているので脳トレをしている子どもとしていない子どもの違いが分かりにくいのですが、今日は、先日入室したお子さまも一緒に取り組んでいたので、脳トレの効果が一目瞭然。
見学していたお母さんもとても驚かれていました。
教室では、みんなが脳トレをしているので気づきにくいのですが、脳トレをしていないお子さまの中では、物の捉え方や視野の広さ、要領の良さなどかなり差がでます。
それも継続することでその差は開いていきます。