9月8日木曜日
1枚の紙にたくさんの折り線をつけて、線を山折り、谷折りで折っていくと立体的なものが作れます。
最初は、1枚の紙でつくれるの?と驚いていましたが、折り線をつけるところまではそんなに難しくなかったのですが…
山折り、谷折りにしていくイメージがなかなかわかなくて、途中から山折り、谷折りが逆になって形が違う方に・・
いろいろ試行錯誤してやっと完成…
みなさ皆さんも軽く折り紙で軽く脳トレしてみませんか?
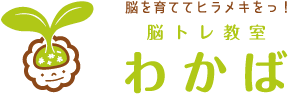
長崎市住吉町にある脳トレ教室

1枚の紙にたくさんの折り線をつけて、線を山折り、谷折りで折っていくと立体的なものが作れます。
最初は、1枚の紙でつくれるの?と驚いていましたが、折り線をつけるところまではそんなに難しくなかったのですが…
山折り、谷折りにしていくイメージがなかなかわかなくて、途中から山折り、谷折りが逆になって形が違う方に・・
いろいろ試行錯誤してやっと完成…
みなさ皆さんも軽く折り紙で軽く脳トレしてみませんか?
3歳になるかんちゃん。
今日は、わかばの積木に挑戦です。
1歳から通いだしてたびたび積木を触って遊んでいたので形の認識ができています。
なので、今日は5歳児用のお手本を使って挑戦です。使う積み木の数も多いので少しお手伝いしながらできるかな?と思っていたのですが、なんと!! 積木をを置きだして形が見えてくると自分で積木を選んで乗せていきます。
隣で見ていたお友達のお母さんも驚いていました。
いやぁ・・・ 実は私も驚いたんです。 凄い凄い!! かんちゃん。
しばらくプールに行けていない山の子たちです。
今日は、プール行きたいね。と言っていたのに・・・あとは大雨 おまけにゴロゴロ雷…
さっきまで雨でも行けるよって言っていたのに、さすがに雷なりだしたからみんな諦めました。
その代わり、部屋の中では反対言葉神経衰弱大会始まりました。
線と点 朝と夕 昼と夜 弱いと強い カートには分り易く絵が描かれているので読めない漢字が出てきても何となく反単言葉が分かります。
今年の子どもたちは、カルタや積木が大好きで学習が終わったら何時間でもパズルやカルタ・トランプをしています。
脳がすごく喜んでいるのが分かります。
「知らないってことは、怖いことですね。」って普段から言っているのに。今日は背筋がぞっとした話…
自分の身体の事、過信したらダメですね。
いつまでも若いつまりでいたのに…
簡単な指の体操をやってみたら…
余りにも手の動きがぎこちなくて…大丈夫、私?って思ってしまった。
簡単にできるゆび運動だから朝晩毎日動かさなきゃ…
お母様方は、まだ若いので大丈夫でしょう・・・
って、これが油断です。指先ちゃんと動くかやってみてくださいね。
難易度:初級 これ初級ですが・・・汗がでますよ
両手の指先をきちんと合わせます。
アドバイス 指を回している間、ほかの指先が離れないようにしましょう。
中指や小指はむずかしいの難しいので少ない回数から練習しましょう
さて、お母さんたちはどれくらい指先をしなやかに動かせるでしょうね。
次回、授業の後、やってみましょうね。練習しておいてくださいね。
今日は大島教室はお休みです。
先日、木工屋さんの端材をたくさんいただいてきたので、今日は孫とそれを使って遊ぶことにしました。
板はヒノキ いい匂いを感じながら作ったのはやっぱりあれです。
板をどう置いたらビー玉が転がりやすいのか、最初はペタンとテーブルに置いただけだったのでビー玉は転がらず…
何回も何回も転がしては、板の向きを変えたり、立てたり・・
やっと少し傾けたらいいことに気づきました。
次は、直ぐに板からビー玉が落ちるので・・・また。どうしようかなぁ…と考えています。
最初は、長くて太いくぎだけだったのでなかなか板に入っていかなかったり、板が割れてしまったり・・・
そういうところで、ばあばが・・・
「そう言えばこんなのあるよ。」と画びょうを出してあげました。
「あっ!!これだったらいいね。」と後は夢中でコンコン コンコン金づちで打ち込んで楽しそうでした。
つい、手伝おうとすると「自分でする。」と言われてしまいました。
夢中になって遊ぶことが脳が喜びます。
今日も楽しい一日を過ごさせていただきました。
地元で木工職人さんをしている方と巡り合うことができ、また、その方も子どもたちの未来のことを考えてボランティアとして自分で考えることの大切さをとても大事に考えて活動をされている方でした。
積木を作ってもらえる方を探している時に本当に偶然出会った方なのに、子どもたちの未来に対しての考えが一致しこれから木を使って五感を刺激していくワークショップなども一緒にやっていこうと意気投合しました。
今年は、新しい積木を使った夏休み自由研究を提案したいと思います。
お子さま方が自分で考えたくなるような習慣づけの第一歩
ぜひ、積木遊びをお役立てください。
今回の積木は、ヒノキで出来ているのでとてもいい香りです。
手触りもいいでいいですよ。絵になる部分の積木は着色をやめ自然の木の色を活かして落ち着いた色にしました。
今日は風が強いです。
煽られないように傘を使わなくてもいいように準備が必要です。
皆様の一日が穏やかでいい日になりますように。
西海市大島町には、西海市の文化ホールがありいろんな展示がおこなわれます。
今日まで、西海市出身の田崎観洲さんの水墨画展がおこなわれています。
今回は、絵の説明をQRコードを読み取ってもらうと手話通訳の動画が見られるように工夫しています。
そうなんです。
西海市手話サークル「虹」が協力して手話通訳をしたのです。
昨日、行った時に田崎さんもいらっしゃって手話通訳をつけるにあたっての苦労話を聞いて頂きました。
水墨画と聞くと墨の濃淡で書かれた絵をイメージしていたのですが、田崎さんが書かれている水墨画は、色も使ってあり水彩画より力強く感じました。
今日は、朝から1日机にかじりついて仕事をしていたのでいい気分転換になりました。
今日も皆様の1日が良い日になりますように。
今日は、おばあちゃんのための脳トレ教室でした。
美味しいお団子と美味しいお茶を飲みながらお話したり、クイズを解いたり、パズルをしたり…
私にとっても、いろいろな経験談をお聞きできる日なので脳トレです。
今日はFパズルを使って形作りをしました。
パズルをしている時は、脳の思考回路をパズルの形とお手本の形が情報を交換し合いながら必要な情報を精査して手で片を動かしながら作り上げていきます。
片を動かすためには、もちろん手も動かして掴んだり、きれいに並べたりずっと動いています。
この前、車を整備点検に出したばかりだったので、脳トレってそれと全く同じでその人の持っている能力を最大限に発揮するために大切なこと、整備士の方がボンネットを開けてエンジンルームをのぞき込んでいる姿を見て、私たちがしていることも全く同じことなんだと整備士さんの姿に自分を重ねていました。
国語や算数の学習効率を上げるためには、もちろん復習も大切ですがその前にその学習したことがちゃんと覚えられているか、学習したことが必要な時にちゃんと使えているか、学習効果をしっかり上げるためには、脳のトレーニング(チューニング)はとても大切なものです。
さてさて、今日ははな金!!
皆様の週末が佳き日でありますように。
6月と言えば梅雨入りを控えているのにどうして「水無月」と言うんだろう?
あれ?と疑問に思いませんでしたか? 小学校高学年くらいになると「あれ?」と疑問を持つお子様もいらっしゃると思います。
お母さん方は、たぶん答えを知っていらっしゃる方も多いと思いますが…
「あれ? 去年子どもと一緒に調べたのに…どうしてだったかな?と忘れている方もいらっしゃると思います。」
お子さま方に聞かれる前に思い出しておいてくださいね。
さてさて、成長とともに、子どもたちは必然的に良い時にも悪い時にも直面します。
こんな風に考えたことがあるとありませんか?
この子たちはどうやって自分で問題を解決できるようになっていくのだろう?
自ら考えられる人に育てるために、親として何ができるのだろう?
正しい考え方や価値観を身につけさせるためには、どうすればいいのだろう?
何よりもまず、何から始めればいいのだろうか?
私たちは、こう考えます。
これらすべては、一つの発想にたどり着くと信じています。それは「遊び」です。
大人と同じように、どの子どもも様々な方法で学ぶ力を持っています。それを認識しているかどうかに関わらず、すべての子どもが自然に学びたいと思っており、「遊び」が学ぶための主な方法の一つなのです。
子どもは、遊びを通して学びます。
最も重要なのは、遊びの中で子どもたちは学び方を学んでいるのです。
遊ぶことは、子どもの不可欠な要素です。
それは、子どもたちが素晴らしい大人になるために必要な、認知的スキル・社会情緒的スキル・問題解決能力を学び、身につける過程における生命線です。
子どもたちは、遊びを通して、学び、成長します。
その中で、親や教育者が担うべき役割があります。
これが、決まった答えのない遊びの考え方です。
これにより、枠にとらわれずに考え、新しい視点から物事を捉えられるようになります。
探求し、観察し、実験し、そして問題を解決する機会を子どもに与えるのです。
それが 「わかば」 の基本理念です。
その上で私たちがさらに目指すのは、人格づくりを助ける楽しいチャレンジをお届けすることです。
積木やパズルを使って形を作ってみる。 ある形を分析してどんな形をどんなふうに合わせてできているのかを分析する。 試行錯誤しながらいくつ答えを探し出せるのか。
それは、子どもたちの集中力、我慢強さ、根気強さ次第です。
まるで人生と同じではないでしょうか?
困難な状況との遭遇は避けられません。
失敗することもあります。
しかし、失敗と成功が対極にあるわけではありません。
失敗は、成功するための過程に過ぎません。
大事なのは諦めないことであり、子どもたちもそれを理解していることが重要です。
つまづいて転ぶことが、終わりではないのだと知っておく必要があります。
立ち上がり、進み続けなければなりません。
そうするにはどうしたらいいのかを、知っておく必要があるのです。(この体験は生きる力に繋がります。)
わかばでは、只今若干名お友だちを募集しております。
お子様と仲の良いお友達をご紹介いただけると嬉しいです。
生きる力を持っているお子さま方が繋がっていくと日本の将来は明るく暮らしやすい社会に変わっていきます。
今日も皆様のいちにち1日が穏やかなわくわくルンルンでありますように
世界が平和でありますように
早いものでもうすぐゴールデンウイークですね。
大人の脳トレ教室で、こいのぼりを作ることにしました。
なので、今日は材料を買ってきて1人分ずつカットしてセットします。
お手本の「こいのぼり」を見て簡単に作れそうだと思って決めたのですが・・・
準備が大変!!
今回ばかりは、もう少し考えて決めればよかった。とフェルトに印をつけながらふーっとため息1つ
で、もっと簡単にできないものかと途中から考えて簡単な方法を思いつきました。 脳トレやっててよかった。
さあ!! みんなかわいいこいのぼりを見て喜んでくれるかな。