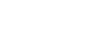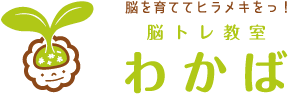「今日の給食、何だった?」から始まる学び
今日、5年生の子どもたちと「給食」について話をしました。
ところが——。
お昼に食べたばかりなのに、何を食べたのか、どんな献立だったのか、
すぐに答えられない子が多かったのです。
そのことを、お迎えに来られたお母さん方にお話ししたところ、
あるお母さんが家に帰ってから「今日の献立は八宝菜でした」と連絡をくださいました。
さらに、「どうして“八宝菜”って言うんだろう?」と、
親子で一緒に料理の名前の由来を調べてくださったそうです。
ほんの小さな出来事ですが、
「調べてみよう」とお母さんが働きかけることは、
お子さんの“学びの姿勢”を育てる大きなきっかけになります。
わかば脳トレ教室では、
こうした“日常の中の気づき”や“親子の対話”を大切にしています。
学びは特別なものではなく、毎日の暮らしの中にあふれています。
ちなみに、八宝菜の名前の由来ご存じですか?
宝菜の名前の由来は、「八」が「たくさんの」、「宝」が「貴重な」、「菜」が「料理」を意味し、
「たくさんの宝を集めて作ったように美味しいおかず」という意味が込められているようです。
「八」は8種類という意味ではなく、日本でいう「五目」と同じように「多くの」という意味で使われています。
八宝菜は、豚肉、エビ、イカ、キノコ類、タケノコ、ニンジン、白菜、ピーマン、うずらの卵など、
多種多様な具材を炒め、とろみをつけた中華料理です。
八宝菜の起源には諸説あります。 清の時代の政治家である李鴻章が、友人の家で食べた五目うま煮を気に入り、
料理人に研究させて生み出したという説。
清の第六代皇帝である乾隆帝がお忍びで入った料理屋で、あり合わせの材料で作られた料理を気に入り、
「八宝菜」と名付けられたという説。
宮廷の料理人たちが残り物で作ったまかない料理を、皇后が気に入り「八宝菜」と名付けたという説。
また、八宝菜をご飯の上にかけたものは「中華丼」と呼ばれ、これは日本発祥の料理だそうです。
こういう豆知識って、意外と役に立ったりするんですよね。