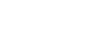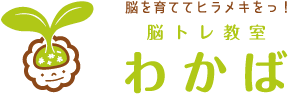お盆休み第2弾
昨日は、空が真っ赤に焼けてすばらしい夕焼けがみられたのですが、運転中だったので写真にとることができず、今日、リベンジに行ってきました。
でも、昨日ほどの夕焼けがみられずちょっと残念でした。
皆さんは、夕陽眺めることありますか?
たまには、ぼーっと眺めてみることをすすめします。
眺めることだけでも心や身体にいくつもの良い影響があります。
夕陽を眺めることは、ただの「きれいな時間」以上に、心や体にいくつもの良い影響があります。主な効果を整理すると、こんな感じです。
1. 心を落ち着ける効果(リラックス)
夕陽のオレンジ〜赤の光は、交感神経の緊張をゆるめ、副交感神経を優位にします。
「1日の終わり」という区切り感が、頭の中の切り替えスイッチになりやすいです。
2. 幸福感や安心感の向上
自然の美しい景色を見たとき、人の脳ではセロトニンやドーパミンが分泌され、穏やかな幸福感をもたらします。
オレンジ色の光は心理的に「安心・ぬくもり・やすらぎ」の感情を引き出します。
3. マインドフルネス効果(今ここに意識を向ける)
夕陽は刻々と色や形が変わっていくため、自然と「今」に集中できます。
雑念が減り、瞑想に近い効果を得られます。
4. 体内時計の調整
日の入りを目で感じることで、脳の「視交叉上核」が体内時計をリセットし、睡眠リズムが整いやすくなります。
夜のメラトニン分泌がスムーズになり、眠りやすくなることも。
5. 創造性や感性の刺激
光と影、色のグラデーションは美的感覚や想像力を刺激します。
詩や音楽、絵など、創作のインスピレーション源にもなります。
日々のストレスや頭の中のざわつきを落ち着けたいなら、
夕陽は「一日の心のクールダウン装置」みたいな役割をしてくれます