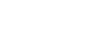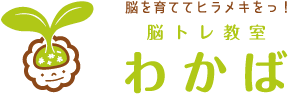今日は何気に通勤タイム車の中でEテレを見ました。
運転しながらですから見るというよりは聞いている。の方が正しいかな?
最初は現代国語 国語が苦手な私としてはチャンネルを変えたい気持ちをぐっと抑えて、どんなことを勉強しているのだろうとそのまま聞いてみることにしました。
今日は、問いを作るという課題でした。
内容は、きっと長い文章を読んでその中で問いを作っていくのかな?と思っていたのですが…
ライオンが牛を食べようと思ったのですが、牛は3匹いたので近づくことができずに食べられませんでした。
そして、ライオンは牛が1匹ずつ暮らすように仕向けて牛を3匹食べてしまいました。
というお話を聞いた後に、いろいろな問いを考えるのです。
どうして牛は3びきいたの? とか、 ライオンはどうやって牛をばらばらに住まわせられたの?
牛は美味しかったの?
いろいろ問を作った後は、その問いが開かれた問か、とじられた問かで分類します。
とじられた問は、「はい」「いいえ」だけで答えになるもの。
開かれた問は、それ以外の問です。
そして、それぞれ分類した後、次は、とじられた問を開かれた問になるようになおします。
開かれた問も閉じられた問になおします。
最初は、苦手意識がありあまり興味がありませんでしたが…次第に話に引き込まれていきます。
そして、誰かに質問する時は自分がどういう答えを求めているかで質問の内容を考えてしないといけないということに気づいていきました。
私が学生の頃にこんな授業の形だったら、もっと表現力や理解力もアップしていただろうなあ…と考えました。
2時間目は、古文 漢詩を読むのですが… なんと、ラッパーの人がゲストで・・・
漢詩ってラップを作る時の言葉の並びに似てるんですって・・・ 驚き…
それから、数学…続きますよ。
三角形のコサイン、タンジェント 三角形の定理を使って辺の中さや角度を求めたり、どんな三角形かを考える。
図形はとくいだったのでちょっとなつかしと懐かしくたのしくみられました
今日は、3番組見ました。 チャンネル替えなくてよかったぁ…
学ぶって楽しいんですよね。 これを勉強嫌とか、めんどくさいって言っている子どもたちに伝えたい。
こんな風に1日が始まりました。 今日は忙しい1日です。