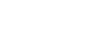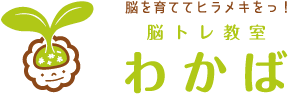遊びの中の脳トレ効果 決まりを見つける遊び
日常生活の中でちょっと意識してお子様の様子を観察するといろいろなことに気づくことができます。
そして、そこでちょっと声掛けをしてあげることでお子様の好奇心のスイッチを入れることができます。
このスイッチが入ると、遊びがより楽しくなり考えたり、継続して遊ぶことができるようになります。
周りの大人がちょっと意識して声掛けするだけでお子様の能力はぐんと伸びだします。
今日はお様方も大好きな繰り返し遊びながら規則性に気づく遊びの脳の働きと学習効果をお知らせします。
色の並びから“きまり”を見つける遊びで育つ力
■ どんな遊び?
たとえば、赤・青・赤・青…と並んだ色を見て、「次は何色?」と子どもに考えてもらう遊びです。
色ビーズやカラーブロックを使って繰り返し並べたり、自分で続きを作ったりします。
■ 脳のどんな働きが刺激されるの?
脳の部位・機能働きの内容前頭前野(思考・推理)規則性を見つけ出す論理的思考力を刺激します。ワーキングメモリ(記憶)並びの順序や法則を一時的に記憶し、次に使う力が鍛えられます。注意・選択の力色の変化に注目し、パターンを読み取る集中力が育ちます。言語領域「赤の次は青!」など言葉で説明することで、表現力も高まります。
■ 遊びを通して育つ力
きまりを見つける力(論理的思考)
先を予測する力(予測力)
比べて違いを見つける力(比較・分類力)
集中してやり抜く力(注意・持続力)
自信をもって説明する力(伝える力)
■ ご家庭での取り入れ方
色だけでなく「大・小」「長・短」「音の高さ」など、さまざまな“きまり探し”で応用ができます。
一緒に「次は何かな?」と考えたり、「どうしてそう思ったの?」と理由を聞いてみましょう。
お絵かきやブロック遊びの中でも、自然に取り入れることができます。
脳トレ教室わかばより
規則を見つける遊びは、小学校以降の算数・読解にもつながる大切な“考える力”の土台を育てます。遊びの中で、楽しく思考力を伸ばしていきましょう。