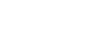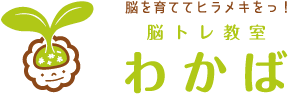6月と言えば梅雨入りを控えているのにどうして「水無月」と言うんだろう?
あれ?と疑問に思いませんでしたか? 小学校高学年くらいになると「あれ?」と疑問を持つお子様もいらっしゃると思います。
お母さん方は、たぶん答えを知っていらっしゃる方も多いと思いますが…
「あれ? 去年子どもと一緒に調べたのに…どうしてだったかな?と忘れている方もいらっしゃると思います。」
お子さま方に聞かれる前に思い出しておいてくださいね。
さてさて、成長とともに、子どもたちは必然的に良い時にも悪い時にも直面します。
こんな風に考えたことがあるとありませんか?
この子たちはどうやって自分で問題を解決できるようになっていくのだろう?
自ら考えられる人に育てるために、親として何ができるのだろう?
正しい考え方や価値観を身につけさせるためには、どうすればいいのだろう?
何よりもまず、何から始めればいいのだろうか?
私たちは、こう考えます。
これらすべては、一つの発想にたどり着くと信じています。それは「遊び」です。
大人と同じように、どの子どもも様々な方法で学ぶ力を持っています。それを認識しているかどうかに関わらず、すべての子どもが自然に学びたいと思っており、「遊び」が学ぶための主な方法の一つなのです。
子どもは、遊びを通して学びます。
最も重要なのは、遊びの中で子どもたちは学び方を学んでいるのです。
遊ぶことは、子どもの不可欠な要素です。
それは、子どもたちが素晴らしい大人になるために必要な、認知的スキル・社会情緒的スキル・問題解決能力を学び、身につける過程における生命線です。
子どもたちは、遊びを通して、学び、成長します。
その中で、親や教育者が担うべき役割があります。
- 個々の長所を引き出すのを手伝う
- 創造性を表現しやすい環境をつくる
- 想像力を働かせる機会を与える
- 本質的な知的能力を養う手助けをする
これが、決まった答えのない遊びの考え方です。
これにより、枠にとらわれずに考え、新しい視点から物事を捉えられるようになります。
探求し、観察し、実験し、そして問題を解決する機会を子どもに与えるのです。
それが 「わかば」 の基本理念です。
その上で私たちがさらに目指すのは、人格づくりを助ける楽しいチャレンジをお届けすることです。
積木やパズルを使って形を作ってみる。 ある形を分析してどんな形をどんなふうに合わせてできているのかを分析する。 試行錯誤しながらいくつ答えを探し出せるのか。
それは、子どもたちの集中力、我慢強さ、根気強さ次第です。
まるで人生と同じではないでしょうか?
困難な状況との遭遇は避けられません。
失敗することもあります。
しかし、失敗と成功が対極にあるわけではありません。
失敗は、成功するための過程に過ぎません。
大事なのは諦めないことであり、子どもたちもそれを理解していることが重要です。
つまづいて転ぶことが、終わりではないのだと知っておく必要があります。
立ち上がり、進み続けなければなりません。
そうするにはどうしたらいいのかを、知っておく必要があるのです。(この体験は生きる力に繋がります。)
わかばでは、只今若干名お友だちを募集しております。
お子様と仲の良いお友達をご紹介いただけると嬉しいです。
生きる力を持っているお子さま方が繋がっていくと日本の将来は明るく暮らしやすい社会に変わっていきます。
今日も皆様のいちにち1日が穏やかなわくわくルンルンでありますように
世界が平和でありますように