9月22日 金曜日
来年のことを言うと鬼に笑われるそうですが…
笑い文字では、年賀状講座に向けて来年の干支、辰をどういう風に描こうかと研究中です。
ありがとう講座を受けられた方が「あ」の書き方を参考にしながら書けるように今年もかわいいデザイナができましたよ。
10月の後半くらいから年賀状開催しますので、家族やお友達など近しい方にはぜひ手書きの年賀状を出されてみませんか。
きっと、届いた方は一年間見えるところに飾ってくれること間違いなし!!
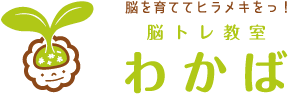
長崎市住吉町にある脳トレ教室

ブログページです
来年のことを言うと鬼に笑われるそうですが…
笑い文字では、年賀状講座に向けて来年の干支、辰をどういう風に描こうかと研究中です。
ありがとう講座を受けられた方が「あ」の書き方を参考にしながら書けるように今年もかわいいデザイナができましたよ。
10月の後半くらいから年賀状開催しますので、家族やお友達など近しい方にはぜひ手書きの年賀状を出されてみませんか。
きっと、届いた方は一年間見えるところに飾ってくれること間違いなし!!
教室が・・・水浸しです。
教室の外カベのどこかがひび割れているらしく、最近の強い雨風の時に水が室内へ入ってくるようになりました。
ここの場所へ移動してすぐにそういうことがあったのですが、その後、台風並みの風雨がなかったためにしばらく忘れていたのですが、
ここのところ、雨のたびに窓際に水たまりです。
電気の配線もあるので何とかしてほしいのですが、どこから入っているのかが分からないらしくすぐに改善される様子でもありません。
どうしたものかなぁ…と、窓を眺めながら考えました。
昨日は、久しぶりにマタニティー講座を行いました。
もうすぐ会える赤ちゃんのことや赤ちゃんを迎えるための家族の役割分担の大切さ
歌らしい命が宿った大きなおなか 見ているだけで幸せをただきました。
生まれたらまた会いたいですね。 元気に生まれておいでね。 待ってるからね。
えっ!! 気が付くと9月もあと10日ほど・・・
いや~時間の過ぎるのが早いというのか、仕事がさばけなくなっているのか…
がんばらなければ・・・
でも、無理は禁物ですね。 気持ちをリラックスさせて作業効率を上げていきましょう。
今日も1日楽しみます。
今日は、敬老の日ですって・・・
母がなくなり・・・とうとう、私にフォーカスする日になりました。
いつもありがとうね。と言ってもらうとまだまだ頑張らなきゃって元気が出てきます。
まだまだ、ばあばは頑張るよ。
今日は午前中、大島教室補講授業でした。
秋になり子どもたちの取り組みがとても良くなってきたんですよね。 秋ってやはり実りの秋ですよね。
楽しみ楽しみです。
今日は久しぶりの日曜お休みの日です。
最近、日曜日にもいろんな用事が入ることが多くなり、今日は自宅にいて教材作ったり、三線練習したり、ゆっくり過ごそう・・・なんて思っていたのに、なんだかんだやらないといけないことを思いだし…バタバタと1日が終わってしまいました。
私は、一人暮らしなので自由に時間を使えるのですが、ママは大変ですよね。
家族のお世話をしながら自分のやりたいこともやって…
今想うと、本当に子育てしている時は自分のことは後回しで結局自分の時間は取れていなかったですね。
その分、今は24時間自分のために使えるのでこの時間を自分のために楽しく使っています。
子育てで大変な時間って今考えるとあっという間に過ぎてしまっているので、大変だけどたくさんお子さまと関わって思い出をたくさん作ってくださいね。
今日は大島教室です。
教室の周りもすっかり秋らしくなってきました。
秋の虫の音も聞いてて癒されますね。
鈴虫やコオロギが多く鳴いています。
最近は、お天気が不順で今日も晴れているのかと思っていたらザアーっと雨が降ってきたり…
あっ!! 雷がすごいですね。
今日来ていた子どもたちが話していたのですが…お家の近くに雷が落ちたらしく、テレビが壊れた家や冷蔵庫が壊れた家がありました。
子どもたちって雷は大きな音がしてぴかぴか光って怖い!!だけかと思っていたようで、電化製品が壊れるのが不思議そうでした。
こんな体験をしたときに、どうしてそんなことが起きるのかを一緒に調べてあげると雲と電気の関係などが分かりますよね。
体験から学習することが一番身につきます。
今日は全く私事で・・・
昨日、プロ野球で阪神タイガースが「アレ」を18年ぶりに成し遂げました。
教室の近くのたこ焼き屋さんは、大のタイガースファン もう、マジックが出てからほんと眠れない夜だったと思います。
タイガースの優勝が18年ぶりだったそうで、私は、自分がプロ野球をみなくなって18年も経っていたんだと気づかされました。
じつは、私、大のGファンでして・・・夫は、関西人なので生粋のタイガースファン
関西人のタイガース愛って本当にすごいんですよね。
プロ野球のシーズンになるとテレビの前で沈黙の戦いを繰りひろげていて、週末の試合結果が次の対戦まで尾を引くということがよくあったことを、優勝を伝える番組を見ながら懐かしく思い出していました。
主人がいなくなり、気が付けばプロ野球を見ることもなくなっていました。記憶をたどると星野監督の胴上げなので18年前の阪神の優勝した年から見ていないことになります。
スポーツを見ることは好きでバスケットやら、サッカーやら見るのですが特定のチームをたこ焼き屋さんみたいに心から応援するということがなかったので・・・優勝で歓喜溢れてたこ焼き屋さんのお店の前でビールかけしている人たちをみてなんか心がほわっと暖かく感動しました。
阪神タイガースの選手の皆さん 岡田監督 タイガースファンの皆さま 本当におめでとうございました。
今日通勤途中で流れていた教育番組
子育ての悩みをスタジオと家庭をオンラインで結び、子育てのお悩み質問コーナーでのこと。
4歳くらいのお子様がゲームが大好きで、お母さんはゲームを与えることを躊躇していたけど、結局、30分と言う制限つきでさせることになったんだけど、ゲームはさせない方がいいのでしょうか・と言う質問でした。
スタジオにいらっしゃる先生の答えが、ゲームはとても強い刺激を脳に与えるのでそれに慣れてしまうと柔らかい刺激に対して興味を示さなくなめることがあるので、時間を決めて取り組ませることは大切です。と言う回答でした…
まだ4歳 時間の感覚はできていません。
30分でも、強い刺激に慣れてしまうと脳は、次第に30分では収まらなくなります。どんどんゲーム時間が長くなってしまうので、まだ、年齢が4歳でしたら私は、ゲームは早すぎるのでまだ与えないでください。とお話しします。
脳は一度強い刺激を受けてしまうと本当に何事に対してもアナログ的なことが面倒になったしまうので、せめて、小学校に入学するまではゲームは与えないでほしいですね。
今日は、大島教室です。
体調不良でお休みのお子様がいて今日はちょっとさみしい教室ですが…
夏の暑さが随分和らぎ、しっかり考えるようになってきました。
先生はとても嬉しいです。
この1年の集大成 ここでぐんぐん力を伸ばして、いろんなことをいろんな方向から考えてみようね。
考えるって楽しいね。