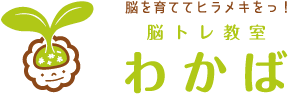
長崎市住吉町にある脳トレ教室

ブログページです
ハンドマッサージが脳に与えるやさしい効果
1. オキシトシン(愛情ホルモン)の分泌
手と手がふれあうと、脳から「安心」や「信頼」に関係するホルモン「オキシトシン」が分泌されます。
このホルモンは、不安をやわらげ、心を落ち着ける働きがあります。
2. 副交感神経が優位になり、リラックス状態へ
やさしく触れるマッサージは、自律神経のうち「副交感神経」を活性化します。
これにより脳が「安心モード」に切り替わり、深いリラックス状態になります。
3. 記憶力や集中力を高める土台作り
脳が安心・安定すると、子どもの学習や遊びに集中しやすくなります。
「こころが落ち着いていること」は、学びや社会性を育てる大事な土台なのです。
4. スキンシップで自己肯定感アップ
親からのやさしいふれあいは、子どもの「自分は大切にされている」という感覚につながります。
これが自己肯定感や社会性の発達を支え、脳の成長にも良い刺激になります。
まとめ
ハンドマッサージは、脳をリラックスさせ、心を育てるやさしいコミュニケーション。
香り(アロマ)とふれあいの力が合わさることで、脳と心にじんわり届く時間になります。
図形や数量、測定といった分野は、小学校中学年から一気に難易度が上がります。
でも、その力は急に育つものではありません。
「形の感覚」「量の感覚」「空間のイメージ」――
これらの土台となる力は、実は 0歳から6歳のあいだに、
遊びや生活体験を通してじっくり育まれていくのです。
この時期に 「考えるって楽しい!」「できた!」という小さな成功体験 を重ねていくことで、
その後の学びの吸収力や理解力がまるで違ってきます。
ごめんなさい。掲載チラシは、他社さんのチラシです。とってもよくまとめられていたのでご紹介させていただきました。
学校帰りに来られるお子様方も一生懸命傘をさしてこられるのですが、傘から垂れてくる雨だれで結構濡れてこられるので、ランドセルにTシャツや靴下の替えを入れていただけたら、授業の間寒くないと思いますのでよろしくお願いいたします。
明日からは、少し梅雨の晴れ間がみられるようですが、今年の夏はきっと熱いのでしょうね。
どんな対策を考えていらっしゃいますか?
夏を涼しく快適に過ごす方法 いいアイデアがあったら是非、教えてくださいね。 よろしくお願いします。
脳トレ教室といっても何をしているのか、外から見ている人には分かりにくいということが最近になってわかりました。
教室の中にいて、脳トレをしっかりしているお子様方を見ていると、楽しいばかりで「これでいいのだ」と大満足していたのですが…
最近、なかなか新しいお友達が来られないなあ…と思い、周りで子育てしている人たちの悩みなどを尋ねてみました。
・落ち着きがない ・最初からできないと決めつけてやろうとしない ・言葉が足りなくてお友達とのトラブルが多い などなど悩んでいるお母さんたちがたくさんいることを知りました。
だったら、脳トレ教室に来てください。
脳トレ教室では、「どうせ無理」が「やってみたい」に代わる場所です。
昨日の、3歳児の授業内容を少しお知らせします。
アンパンマンが大好きなこの世代のお友達たち
今日も、アンパンマンのスタンプを見つけて、ぺたぺた押して遊びだしました。
黙って遊ばせると、次々と新しい紙にぺたぺたおして、しばらく遊んで飽きて終わり。です。
しかし、脳トレ教室では、一枚目の紙にぺたぺたお子様が押して遊んでいるときに、横で、別紙にスタンプ2種類のスタンプを5個くらい押します。
そして、遊んでいるお子様に、先生の見てと言って注目させ、先生の押したスタンプ、◎◎ちゃんの押しているスタンプと同じのある?と声かけます。
すると、自分が押したスタンプと先生が押したスタンプを見比べ始めます。
見つけると「あった」と指さしてくれます。「あったね。ひとつだけかな?」と声をかけるとまた探します。それを繰り替えし、5個探したところで「たくさんあったね。先生の押したスタンプ手をつなぎたいから線でつないでもらえる?」と鉛筆を持たせてあげます。そうするとここでまた新しい遊び道具が出てきて気持ちが変わります。
最初のスタンプから順番に線でつないでいきますが、その時に、私がつなぎ終わったスタンプに1、2、と数字を書いていきます。
つなぎ終わったときに、1から5までの数字を見ながらこの順番に、手をつないだんだね。と1番目2番目「あれ?3番目はどこだった」と声をかけて探させます。
線をヒントに考えます。
ここまでの遊びで、スタンプを押す。という行動で、順番を表す数字、量を表す数字があることを遊びながら体験します。
この体験をした後は、生活の中でその都度、「いくつある?」「何個だった」「2と3だったら、どっちが多い?」「1の次はなあに?」エレベーターなどに乗っているときに「1階の次は何階?」と声をかけて確認したりすることで自然に数量や順番について興味を持つようになります。
また、鉛筆を持たせて線を書かせることで、最初は薄い線ですが、次第にしっかり力強い線が書けるようになります。
まだままだまだ遊びは続きますが、脳を鍛えるということは、生活の中を通してお子様の興味に合わせて楽しく行えるのです。
脳トレ教室わかばには、 お子様を賢くするヒントがたくさんあります。
将来、自分の進みたい場所へ行けるように楽しく無理なくしっかり準備してあげませんか?
夕陽が沈む時間が少しずつ長くなって外海町の眺めのいい場所まで帰ることができるようになってきました。
夕陽を見ながら海岸に落ちている石を積み上げるとつい夢中になってしまいます。
それに、たいして疲れてもいないんですが・・・
気持ちもすーっと晴れ晴れします。
石積みには、すごいリラックス効果があったんです。
小さめの石を集めて教室でもお子様方と積んで遊んでみました。
とても喜ばれていろいろ工夫する姿も見られました。
海岸での石積みは、自然とふれあいながら心と脳を整える素晴らしい遊びです。リラックス効果と、それに伴う脳の働きについて以下にまとめました。
● 呼吸が深まり、副交感神経が優位に働き、心身がリラックスします。
● 五感(触覚・聴覚・嗅覚など)へのやさしい刺激が、安心感をもたらします。
● 反復的な積み重ね作業は、瞑想のような効果があり、雑念を手放すことができます。
|
脳の領域 |
働き |
石積みとの関係 |
|
前頭前野 |
思考・感情のコントロール |
積み方を考えることで感情が安定 |
|
頭皮質 |
五感と感情の統合 |
石や自然環境からの刺激を心地よく感じる |
|
海馬 |
記憶・空間認識 |
楽しい体験として記憶され、空間把握も発達 |
|
扁桃体 |
不安や恐怖の処理 |
安心感によって過剰な反応が抑えられる |
|
後帯状皮質 |
自己認識・意識の安定 |
今ここに集中し、心の整理が進む |
石積みは、自然の中で心を落ち着かせながら集中できる遊びです。子どもも大人も、ストレスを和らげ、脳のバランスを整える時間となります。ぜひ、日常に取り入れてみてください。
今日は、パソコンでお仕事していると久しぶりに角度の問題が出てきました。
皆さんは、この問題わかりますか?
これは、それぞれの角度は計算でわかるのですが、6年生で習う中心角と円周角を知らないと解けない問題です。
小学校6年生では「円の性質(中心角・円周角)」について学習します。この学習では、図形の中にある角度の関係性に気づき、
法則を使って自分で答えを導き出す活動を通して、以下のような脳の働きが刺激されます。
- 前頭前野:論理的思考力、推論力を使って角度の関係を読み解く力が育ちます。
- 頭頂葉(空間認知):図形をイメージで捉え、構造を把握する力を高めます。
- ワーキングメモリ(作業記憶):角度の情報を一時的に記憶しながら計算・推論する力が鍛えられます。
- 図形と数の関係に気づくことで、数学的な見方・考え方が深まります。
- 問題を筋道立てて解く力(論理性)が育ちます。
- 自分の考えを図や式で表現し、人に説明する力が身につきます。
「この角度はどれくらいかな?」「なんで半分になるの?」と一緒に考えることで、子どもたちは楽しく学びながら、思考の力を育てていきます。答えを教えるのではなく、気づきを引き出す声かけが効果的です。
■ 遊びの内容
サイコロを転がしてマスを移動しながら、どの面が上になるかを観察します。同じ場所に戻っても、上面の数字が異なることに気づくことで、
「立体の回転」に対する感覚を育てます。
■ 脳の働き
脳の部位働きの内容前頭前野予測・計画
次にどの数が上になるか考える力頭頂葉空間認知
立体の向きや位置を把握する力小脳運動のコントロール
サイコロを丁寧に転がす手先の動き海馬記憶の定着
転がした結果を覚えて比較・予測する力
■ 学習効果
空間認知力の向上
立方体がどのように回転するかを視覚的に理解することで、図形の「裏」「横」「上」といった概念を体感的に学びます。
論理的思考の育成
「この面が上なら、次はどこが上になる?」と考えることで、予測と検証の力が育ちます。
因果関係の理解
転がす順番や方向によって結果が変わることから、「動かし方と結果のつながり」を学びます。
記憶力・注意力のトレーニング
どの面がどこへ動いたかを覚える必要があるため、集中力や短期記憶力が養われます。
■ この遊びのポイント
答えが1つではないので、「試してみよう!」という探求心が育ちます
友だちと一緒に遊べば、自然と会話力や説明力も育ちます
大人が「どうなったかな?」と問いかけることで、考える力がさらに深まります
相手のおはじきを「飛び越して取る」ルールの遊び(いわば簡易版のチェッカーやジャンプゲームのようなもの)は、子どもの脳にとって非常に有効な知育活動です。この遊びによって刺激される脳の働きと、得られる学習効果は以下のとおりです。
【脳の働き】
前頭前野(計画・判断)
先を読んで動かす必要があるため、手番の中で「どう動けば一番有利か」と戦略を立てます。これは前頭前野を活性化し、論理的思考や問題解決力を育てます。
頭頂葉(空間認識)
マス目の中で自分と相手の位置関係、取れる場所の把握などに空間的な把握力が求められ、頭頂葉が活発に働きます。
側頭葉(ルールの理解と言語処理)
遊びのルールを聞いて理解し、それを守って行動することで、ルール理解力や言語処理能力が鍛えられます。
海馬(記憶)
一度成功した動きや、取られやすい配置などを覚えて応用するため、記憶力が刺激されます。
【学習効果】
論理的思考力の向上
「次にどこへ進むと取れるか」「取られないためにどう避けるか」と考えることで、論理的に物事を考える習慣が育ちます。
注意力・集中力の強化
相手の動き、自分の動き、取れるチャンスなど、複数の情報に注意を払うため、集中力が養われます。
先読み・予測力の訓練
一手先、二手先を予測する力がつき、「考える力」が自然と身につきます。
社会性(ルールを守る・勝ち負けを受け入れる)
ルールに従いながら遊ぶこと、勝ち負けを経験することを通して、社会性や感情のコントロール力も育まれます。