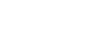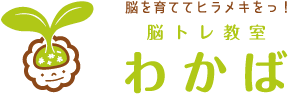■ 思考停止につながる「答え写し」の習慣
◉ きっかけは「わからない」や「面倒くさい」
夏休みの宿題には、普段とは違う環境の中で自分のペースで進めなければならないという難しさがあります。
「ここ、わからない」「時間がかかる」「早く遊びたい」――そんな気持ちから、配られた解答集に手が伸びることがあります。
最初は一部だけだったものが、やがて“答えを見る → 写す”が当たり前の流れになっていきます。
■ 問題を自分で考えなくなると…
◎ 思考力の低下
「自分の頭で考える」経験が減ることで、考える力そのものが育ちません。
特に小学生のうちは、試行錯誤を通して“考える力”を身につける大切な時期です。
◎ 学習の意味が変わる
“学ぶ”ことが「終わらせること」や「怒られないようにすること」にすり替わってしまい、
勉強そのものがつまらないものと感じやすくなります。
◎ 応用力・記憶力が育たない
ただ写すだけでは、内容は頭に残らず、応用問題には太刀打ちできません。
「考えて解いた経験」が、後々の学びの土台になるのです。
■ おうちの方にできること
宿題の進み具合を一緒に確認する時間をつくる
「どこが分からないのか」を子どもに聞いてみる
答えを見る前に、考える時間を少しだけでも取らせる
頑張って考えたこと自体を褒める
■ おわりに
夏休みの宿題は、ただの“作業”ではなく、「自分で考える練習の場」です。
少しの声かけと見守りで、子どもたちは“考えること”の楽しさを思い出します。
「終わらせるための宿題」ではなく、「成長につながる宿題」に変えていけるよう、
この夏、おうちの方の関わりがとても大切です。
お子さまが終わらせた問題の〇付けを楽しんでくださいね。
〇つけから、お子様の考え方や学習に対する取り組みの様子が観察できますよ。