8月27日 火曜日
大島造船所の命名式に参加してきました。
5年ぶりに造船所に行って新しい船の命名式のセレモニーに参加しました。
命名式の日には、大島造船所からピカピカの大型バスがお迎えに来ます。
崎戸地区や大島地区全域をバスが回って島民を造船所まで案内してくれます。
セレモニーは30分ほどで終わりますが、地元の保育園の子ども達が祝いの太鼓をたたいたり、来賓の方々の紹介があったり、賑やかに執り行われました。
青空に新しい船が光り輝いていました。
新しい船は、カナダの五大湖で活躍するそうです。
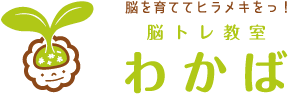
長崎市住吉町にある脳トレ教室

ブログページです
大島造船所の命名式に参加してきました。
5年ぶりに造船所に行って新しい船の命名式のセレモニーに参加しました。
命名式の日には、大島造船所からピカピカの大型バスがお迎えに来ます。
崎戸地区や大島地区全域をバスが回って島民を造船所まで案内してくれます。
セレモニーは30分ほどで終わりますが、地元の保育園の子ども達が祝いの太鼓をたたいたり、来賓の方々の紹介があったり、賑やかに執り行われました。
青空に新しい船が光り輝いていました。
新しい船は、カナダの五大湖で活躍するそうです。
台風が近づいてきているようで、なんだか不安ですね。
夏休みもあと何日かというところで最後の予定変更を余儀なくされた方も多いと思います。
大きな台風になっているようなので皆さまご安全にお過ごしくださいね。
今日は1カ月に一度の大島みやび農園の子ども食堂でした。
野菜の天ぷら(イモ)に、ナスとオクラの煮びたし、いなりずし、オムライス、サラダ、しなちくの煮物、イチジクのケーキ、素麺(ナンプラーのピリ辛ダレ)などなど
懐かしい田舎のおばあちゃんの味
お腹いっぱい頂いて、大人200円 高校生までは無料です。
ぜひ、秋になったらドライブがてら遊びに来てくださいね。
今日は、大島夏祭りです。
沢山の出店やキッチンカーも出店するそうです。
花火もあるそうなので子どもたちは、ソワソワしています。
皆さんは、夏祭りでかけられましたか?
お祭りで何か食べましたか?
金魚すくいとかやりましたか?
コロナ禍で夏祭りを知らない子ども達もいると思います。
やっとお祭りも以前と同じように開催されるようになってきましたね。 よかったよかった。
もう、週末です。
今日は、忘れた水着のことを尋ねるためにプールへ行ってみました。
すると、・・・
「今日は、泳げるよ~」
これは、泳ぐしかない!!
直ぐに子どもたちと一緒に再びプールへ
何と今日も貸し切り状態 大喜びで遊んでいました。
今年3回目のプール遊びができてよかった。
今日は、子ども達がダンスのレッスンに行くので16時半におしまいです。
月曜日が始まると一気に1週間が過ぎてしまう感覚です。
夏休みは、お母さんも大変ですよね。
朝からお買い物に行って、お昼ご飯作って、食べさせて、朝片付けしていると・・・おやつは?・・・
そんなこんなしているうちに、洗濯物を取り込んだり、夜ご飯の支度したり、その間に子どもたちの相手をしたり・・・お風呂に、ねかしつけたり・・・
ほんとお母さん頑張ってますよね。 頭が下がります。
後もう少しですから、疲れをためないようにファイトです。
今日は、海からの風がさわやかです。
今日は、なんとプールが開いているということで子ども達も久しぶりにプールへ行きました。
今年は、閉鎖が多かったので他の子ども達は開いていることを知らずに来ていませんでした。
なので、山の学校の子ども達だけで広いプールで大はしゃぎでした。 良かったね。
プールの監視員さんの話では、気温が上がると閉鎖しないといけないので今日も何時まで泳げるかわかりません。とのことでした。
今までプールでの水遊びは、夏休みの大きな楽しみだったのに来年以降は、プール遊びができなくなる可能性もありますよね。
子どもたちの遊びの環境も随分変化してきていますね。
今年は、プールの閉鎖が続いていてなかなか泳ぎに行けない子ども達です。
シーグラスでも拾いに海に行ってみようか・・・と提案したものの 今は大潮で満潮時間
結局海にも行けず、図書館は? ・・・今日は休館日 なんて日だ!!
山の教室でお昼寝timeとなりました。
お昼寝timeは、極暑のせいで外へも行けず子どもたちの苦肉の策・・・あれ静かになったなぁと思ったら 一人寝、二人寝・・
そのうち皆がお昼寝timeになりました。
来年もこれより高温になったりするのだろうかと考えると怖いですよね。
でも、今年良かったのは、わりと近くに川遊びができる場所を見つけたので機会があったらまた出かけたいと思っています。
お盆休みを頂き、今日からまた、山の学校再開です。
山の学校では、朝、8時から17時半くらいまで子どもたちと一緒に過ごします。
なので、子ども達の傾向がよく見えます。
今年は、たくさんの学びがありました。 このままではどうなるんだろうと思う場面も沢山あり、これからどんなことをしてあげられるのか・・・今年は、限界を感じる場面もありましたが、まだ身体が元気なうちはなんとか子どもたちと一緒に居て、できることをしてあげたい。と想いがこみあげてきました。
さあ、後2週間楽しい思い出作りにがんばります。
今日は、お墓のお掃除に長崎へ
今年は、激暑だったので、お墓の水道が温水器のお湯で、生花を行けるのにお花が可愛そうなくらいでしたが
なんとか、今日まで大丈夫でした。
お墓掃除をして気持ちもすっきりでした。