大島造船所
大島教室のある西海市大島町には、大島造船所という小さいけど大きな造船所があります。
今日は、あたらしい船のひきわ引き渡し式(命名式)
大島の住民が招待されてみんなで新しい船の完成をお祝いします。
子どもたちは、命名式が大好きです。
きれいなバスがお迎えに来るし、帰りにお菓子がいただけるから。
今日のお船もとてもおおきいお船でした。
大島で作っているお船は、ものを運ぶお船だそうです。
命名式があるので、子どもたちは楽しみにしています。
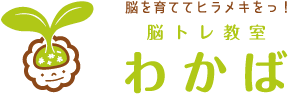
長崎市住吉町にある脳トレ教室

大島教室のある西海市大島町には、大島造船所という小さいけど大きな造船所があります。
今日は、あたらしい船のひきわ引き渡し式(命名式)
大島の住民が招待されてみんなで新しい船の完成をお祝いします。
子どもたちは、命名式が大好きです。
きれいなバスがお迎えに来るし、帰りにお菓子がいただけるから。
今日のお船もとてもおおきいお船でした。
大島で作っているお船は、ものを運ぶお船だそうです。
命名式があるので、子どもたちは楽しみにしています。
今日は、母の三回忌を行いました。
2年前の夏休みに入ってすぐに今まで元気だったのに、コロナ禍で外出や人に会うことができなくなり、
めっきり元気が無くなってしまいました。
外出しないと身体も動かさないし、身体を動かさなければ食欲もなくなるし…
一番心の共にしていた同い年のおばさまがなくなられて一週間目に後を追うようにして旅立ってしまいました。
母は、小学校の教員をしていて、小学校に入学してきた子供たちの学力差に唖然とする。とよく話をしてくれました。
だから、小学校へ入学して困らないように、しっかり好奇心と物事に対して興味を持たせることの大切さを孫育ての時に
実践してくれました。
おかげで、近くにいた孫たちは、健やかに自分らしい幸せな人生を送っています。
私も知能教育には、母の遊びながら好奇心を刺激しそれが知能の発達に結びついていくという理念が生かされています。
私は、父や母を見て自分も教員になりたいと思いました。
父や母の想いをついで子ども達の未来のお手伝いができていることを誇りに思います。
そんなことを想いながら墓前で手を合わせてきました。
私は、どうして一番大事なことをちゃんと伝えるのが下手なんだろうって…つくづく心が折れてしまうことがよくあります。
子どもたちの脳は、思考が柔らかくていろんな刺激を受けやすくしっかり興味付けをして体験させてあげることで、情報を送り合う神経細胞の働きが良くなり、物事も深くしっかり考えられるようになります。
いよいよ11月も後半です。
年長さんは、小学校入学に向けて仕上げの時期に入ります。
仕上げと言っても受験準備ではありません。1年生になった時に、先生がお話していることに気づいて先生の話している内容を理解し指示に従うことができるかを確認して仕上げているのです。
まだ就学前のお子さまですから、自分の話に夢中になって他の人の話を聞けないお子さまや逆に誰が話していてもあまり興味を持たず、話が耳に入っていかないお子さまもいらっしゃいます。
まずは、自分に対して誰かが話しかけていないか。集団の中にいると、自分だけに話しかけられるのではなく全体の中の一人として話を聞かないといけません。
一対一で話を聞けているお子さまも、全体の中の一人としてだと聞き落としたり、自分に言われていないと思って聞いていないことがよくあります。
ご家庭で話を聞くときは、お家の方がお子さまの様子を見ていて、聞いていないようだったら「ほらほら」と意識を話している人に向けさせて聞かせると思いますが、家庭の外では、いつもそんな風に注目させてもらえる環境にはありません。家庭の中ではできるからと安心しないでくださいね。
保護者の方がいないところで出来て初めて「できる」という評価になります。
これから入学までの間は、「家庭の外でできるか」「自分でできるか」「意味が分かるように話ができるか」などを確認しながら入学準備を進めていきましょう。
秋深くなりいろいろなことを考え、想うことが多くなったこの頃
みなさんは、どんなことを想うことが多いですか?
私は、やはり、未来を担う子どもたちのことですね。
時代が変わり子どもたちの成長発育環境もがらりと変わってこれから育っていく子どもたちは新人類と呼ばれたりしています。
生まれてすぐに電子機器に囲まれて1歳くらいになると携帯片手に遊んでいるんですものね。
電子機器が悪い訳ではないのですが・・・
でも、子どもたちは人間なんです。
これからの時代、AIが私たちの生活の中にたくさん入りこんでいろいろと助けてくれるでしょう。
携帯も子どもたちのタブレットも情報を得る一つの道具としてはいいかもしれないけど、それに頼りっぱなしになる(依存してしまう)と人間としてではなく、感情を失くしたロボットに育っていくのではないかと怖くなります。
アスリート教育の世界では、神経回路が急ピッチで進む5歳から8歳くらいの子どもを「プレゴールデンエイジ」そして神経系の発達がほぼ完成に近づいた9歳から12歳頃の子どもを「ゴールデンエイジ」と呼び、一生通用するセンスや技術を身につけられる極めて重要な時間ととらえ、その時期に対応した指導をおこなうことはもはや常識となっているとか。
筋肉や骨などの成長は、ある程度発達した後でも訓練や食べ物によってコントロールすることもできますが、脳神経の回路は一度形成されたものは簡単には消えません。
自転車に一度乗れるようになれば、その後10年乗っていなくてもある程度スムーズに乗ることができます。子どもの頃にある程度の身体感覚を身につけているのといないのでは、その後の運動神経にも大きな違いが出てくるのです。
話しが行ったり来たりしますが、脳は、自分一人だけで伸びていくことはできません。つまり、人間の脳は相手があってこそ才能を発揮できる仕組みになっているのです。